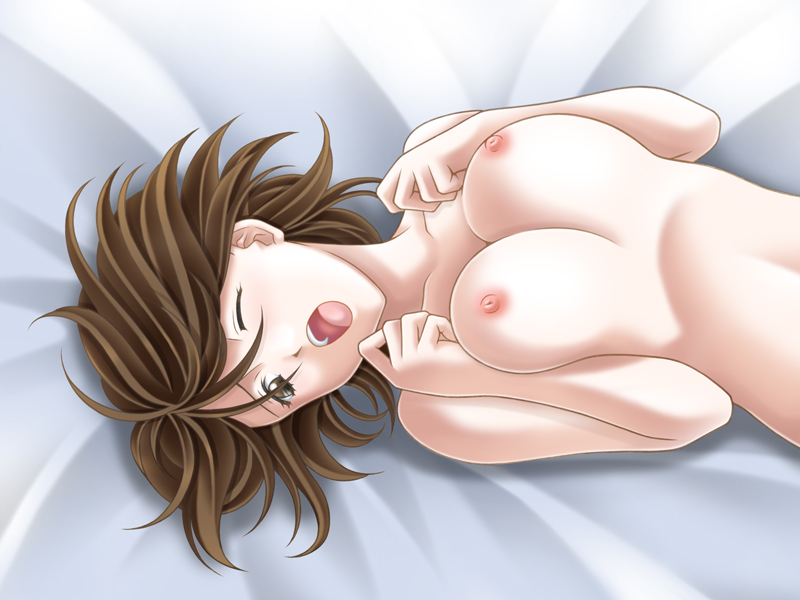
伊藤隆太は地元の高校を卒業してすぐに上京し、安いアパートを借りて暮らし始めた。そして彼は今、都内にある俳優養成所の前に立ち、希望に胸を膨らませる。信じれば夢は叶うものだと、彼は燃えていた。
「よーし、ここが俺の出発点だ。いつかきっと、立派な役者になってやる!」
生活のためのアルバイトも接客中心の居酒屋を選び、挨拶や笑顔の練習をしながら仕事に励んだ。収入はアパート代とレッスン料でほとんどが消えてしまうが、夢を実現させるための投資だと思えば苦にならない。今の隆太にとって、夢を追うことだけが全てだった。
「あのう、すみません」
後ろから声をかけられて振り向くと、隆太と同じ二十歳前くらいの、清楚な白いカーディガンにすその長いスカートを履いた女性が立っていた。さっぱりとしたショートヘアに赤い縁の眼鏡がよく似合う、とびきり可愛い彼女に隆太は目を奪われた。
「ここって、この住所に間違いないでしょうか」
「……へっ。あ、えっと。ごめん、なんだっけ?」
ボーっとして質問を聞いていなかった隆太がもう一度訊ねると、彼女は手にしたメモをよく見えるように差し出す。
「ここの住所です」
「どれどれ……うん、合ってるよ」
「そうですか、よかったあ。私方向音痴なので」
安堵する彼女の微笑が、隆太に鮮烈な衝撃を与える。背骨に電流が走るような、心臓を鷲掴みにされるような一目惚れだった。
「あ、あのさ、もしかして今日からここに入ったりするの?」
「はい。私、女優になるのが夢なんです。最近上京してきたばかりで、右も左も分かりませんけど……」
「へえ、奇遇だなあ。俺も上京したばっかでさ、今日からここで役者目指すんだ。名前は伊藤隆太。ヨロシク!」
「春日愛といいます。よろしくお願いしますね」
「あ、あのさ。実はまだ手続きしてないんだ。一緒に受付行こう」
隆太は内心浮かれつつ愛を連れ、受付でサインと授業料の支払いを済ませ、晴れて養成所の練習生となった。レッスンは週に二〜三回で、しばらくは発声練習や滑舌と言った基礎の繰り返しが続いたが、数ヶ月も経つと台本を使った練習が始まり、ある日のレッスンで二人一組で与えられた役を演じるように言われた。隆太が迷わず立候補すると、相手役に名乗り出たのは愛だった。
「よろしくです、隆太さん」
「こ、こちらこそ」
眼鏡のよく似合う愛らしい笑顔に、隆太の心臓が大きく脈打つ。彼女と真正面から向き合うと、やはり照れてしまうのである。二人は講師から台本を渡され、目を通す。内容はネズミの親分と、気が弱く甘えんぼな子猫の交流を描いた舞台演劇の一部で、保健所の人間に捕まりそうな子猫を逃がすため、ネズミの親分が囮になろうとしている場面である。一通りざっと読んで台詞と流れを頭に入れると、ネズミの親分役を隆太が、子猫役を愛が受け持つ事を決め、演技が始まった。
「――くそっ、人間どもがもうこんな所まで」
「ど、どうしよう……ぼく、捕まっちゃうのかな」
「俺が出て行って連中を引き付けておくから、お前は先に逃げろ。いいな」
「やだよう、一緒じゃなきゃやだっ」
目に涙を浮かべてすがりついてくる愛の表情は、演技とは思えないほど真剣で、隆太が一瞬次のセリフを忘れて見入ってしまうくらいに素晴らしいものだった。
「行かないでよ。ひとりぼっちになったら、どうしたらいいの?」
上目遣いで見上げてくる愛の可愛さは、もはや犯罪と呼べるほどに強烈で。彼女の眼鏡に映る隆太の顔は、茹でたみたいに真っ赤に染まる。
(あああっ、違う違う勘違いするな。これは演技これは演技これは演技これは演技……!)
必死に気持ちを鎮めようとしたのだが、恋愛慣れしていない隆太は、愛の華奢な肩に手を回すだけで心臓が踊り狂い、ほのかに香る彼女の匂いに思わず変な声を出してしまいそうだった。
(落ち着け、落ち着くのだ隆太。ここで役になりきらないでどうする)
高鳴る気持ちを押し殺し、隆太は演技を続ける。
「お前は俺と違って、立派な爪も牙もあるじゃないか。もっと勇気を持てよ」
「そんなこと言っても恐いよ。お願い親分、ぼくと一緒にいて」
「甘えん坊なやつだなぁ、ったく――」
親分はため息をついて子猫の頭を撫でる。台本の通りに隆太は愛を撫でたが、細く柔らかで、絹糸みたいに滑らかな髪に触れるたび、胸の奥がかあっと熱を帯びて仕方がなかった。愛は隆太の胸に顔をうずめ安心しきっていたが、講師が手を叩いて終了の合図をすると、何事もなかったように普段の表情に戻り「ありがとうございました」とお辞儀をした。
レッスンが終わり、帰る方向が同じ隆太と愛は、最寄りの駅に向かって歩いていた。最近では一緒に帰る事も当然となり、色々なことを語り合うこのわずかな時間は、隆太のささやかな喜びだった。
「――いやあ、びっくりしたよ。愛ちゃん演技めちゃくちゃ上手いんだな」
「そんなことないです。隆太さんが頼れる親分の雰囲気出してくれたから、私も上手くやれただけで」
愛の実力は同期の中でも飛び抜けており、すばらしい女優になれる才能を秘めていると、講師が認めるほどであった。その影で隆太の姿勢と演技も良い評価を得ていたが、彼はまだその事を知らない。
「でも、愛ちゃんが凄いってのはみんなが思ってるはずだぜ。講師も褒めてたじゃないか」
「そ、そうかな……えへへ。でも、いつか私と隆太さんと、同じ舞台に立てたりしたら素敵ですね」
「そ、そうだね。俺も負けてらんないなあ。うおーっ、やるぞー!」
気合いを入れ直すために隆太が両手を上げて叫んでいると、携帯電話の着信音が鳴る。愛の携帯電話だった。
「もしもし……うん、ちょうど終わったとこ。うん……うん」
遠慮のない口調から、家族からの電話かなと隆太は察したが、愛の声のトーンはだんだん低くなり、やがて立ち止まって何事か強い口調で話しはじめた。
「わかってる。わかってるってば……ちゃんとやってるよ。うん……だから急には――」
ほどなくして話は終わったが、愛の顔は沈んでいた。初めて見る彼女の表情が気になったが、日々の忙しさに追われているうちに、隆太は次第にその事を忘れていった。
太陽がさんさんと照りつける真夏のある日、珍しく休みが取れた隆太は思いきって愛をデートに誘うメールを出した。期待と不安で落ち着き無く携帯電話を弄んでいると「行きます。どこで待ち合わせしますか」という返事が返ってきて、隆太は喜びのあまりベッドを転げ回った。デート場所は近場の小さな遊園地に決めた。急な誘いでもあったし、入場料も安くてちょうど良かったからだ。
「――へえ、それじゃお化けとか平気なんだ。恐い映画とかも?」
「あれは映像の中の存在ですから。一人でも平気で見てますよ」
歩きながらそんな話が出たので、最初に入るアトラクションを決めかねていた隆太は、お化け屋敷に入ることにした。お化けが出てきたら、二人で笑い飛ばしてやろうと思ったのである。入り口で料金を払い、真っ暗なお化け屋敷の通路を隆太は進む。
「さーて、どこから出てくるんだあ?」
「ま、待って隆太さん」
「えっ?」
「あ、あんまり離れないでください」
そう言って愛はぴったりとくっついてくる。
(ああ、そうか。眼鏡かけてるくらいだし、周りが見えないんだな)
一人で先に行こうとしたことを反省し、隆太は愛に歩幅を合わせ、ゆっくりと進む。やがて緑色の薄暗い照明に照らされた、古ぼけた社が現れた。いかにも「出ます」といった風情で、どこから来るのか待ち構えていると、けたたましい音を立てて社の戸が開き、同時に愛が立っている左側の壁から血まみれの落ち武者人形が飛び出してきた。
「おおっ、こっちとは意表を突かれた」
言いつつ隆太は余裕だったが、愛は声も出さず隆太にしがみついている。
「あれ、どうしたの?」
「えっ、その……びっくりして」
「怖いの平気なんじゃなかったっけ」
「へ、平気ですよ。でも」
「だいじょぶだいじょぶ。こんなの作り物だってば」
落ち武者のおでこをつんつんと指で押し、隆太は先へ進む。すると今度は左右の障子からたくさん腕が出るわ大きな音がするわ、最後に生首の作り物が天井から降ってくる。
「きゃーーーーっ!」
途端に愛は絶叫し、隆太の後ろに隠れてしまった。
「あ、愛ちゃん?」
「だ、ダメなんです私。こういうのダメなんですっ」
「えっ、だって怖い映画も一人で見るって」
「これは現実じゃないですか。それに暗いし狭いし、急に出てくると怖くて……」
(うわ、やっちまった)
隆太は愛をお化け屋敷に連れて来たのを後悔し、目の前にぶら下がっている生首を忌々しげに追い払う。
「ごめん愛ちゃん。俺、怖がらせようなんて思ってなくて」
「隆太さんは悪くないですよ。でも……離れないでくださいね」
「そ、そりゃもう」
左腕に密着するぬくもりと柔らかい感触は、思わぬ役得だった。
(こ、これは思ったよりもっ。結構着やせするタイプだったとは)
漫画やドラマでよくあるこんな場面を、ちょっぴりでも期待しなかったといえば嘘になる。それがほぼ理想どおりの形で現実になったのだから、思い残す事は無いとさえ思うほど幸せだった。やっとのことでお化け屋敷を抜け出した後は、夏限定の極寒アトラクションというのがやっていたので、そこに入ってみた。南極の気温を再現したという部屋の寒さは尋常ではなく、暑さで滲んでいた汗が一気に凍り付いてしまうほどだった。
「うひー、いくらなんでも寒すぎだろ」
「め、眼鏡が」
愛の眼鏡は、寒さのおかげでレンズに霜が着いて真っ白になっていた。愛は冷え切った赤い眼鏡を外し、指で霜を落としていく。
(か、可愛い)
眼鏡を外した素顔もそうだが、ちょっと困った顔で眼鏡を拭く仕草に愛嬌があって、隆太はつい見入ってしまう。
「あのう」
「……はっ」
「私の顔になにかついてますか?」
「つ、ついてないよ。眼鏡はついてる――って、そうじゃなくて、えーと。その眼鏡いつもしてるんだね」
「お気に入りなんです、これ。近視で昔から眼鏡を掛けてるんですけど、高校の卒業祝いに作ってもらったんです」
「へえ、そうなんだ。可愛いしよく似合ってるよ」
「あ、ありがとうございます……」
褒められた事が嬉しかったのか、愛は顔を赤らめてうつむいてしまう。どちらかが言い出すでもなく二人は自然に手を繋ぎ、歩き始めるのだった。
遊園地を一通り回る頃には日も暮れ始め、幸せな時間にも終わりが近付こうとしていた。
「あー遊んだ遊んだ。急な話だったのに付き合ってくれてありがとう、愛ちゃん」
「大丈夫ですよ、私も休みでしたし。今日は本当に楽しかったです」
「うおお、そう言ってもらえると感激だなあ」
「あ、あの、隆太さん。また機会があったら誘ってくださいね」
「そ、それって……」
続きを聞こうとしたその時、携帯電話が鳴った。聞き覚えのあるメロディは、愛の着信音である。着信表示を見た愛の顔には陰りが差し込み、深刻な口調で話し込んだ後、いつか見た時と同じように沈んだ表情で電話を切った。うつむいて黙り込む愛が心配になり、隆太は訊ねた。
「あ、あのさ。家族とモメてるの? お節介かも知れないけど、俺で良ければ相談に乗るよ」
「ごめんなさい隆太さん。嫌なところを見せてしまって……でも、大丈夫です」
「そ、そうだよね。あはは」
「隆太さん」
「えっ」
「私、用事が出来てしまったので、今日はここで失礼します」
返事を待たず、愛は一人で掛け去っていく。隆太はその場に立ち尽くし、彼女の小さな背中を呆然と見送っていたが、やがて気を取り直して歩き出す。一緒に帰れなかったのは残念だが、またすぐに会える。彼女が悩みを抱えているなら、今度じっくり聞いてやろう。そんな事を、一人で考えていた。
ところが次のレッスンから、愛の姿が消えた。気になって電話やメールをしたが、まったく返事が返ってこない。講師に聞いても知らないという。隆太は居ても立ってもいられなくなり、アルバイトの帰りに愛が住んでいるマンションの前までやってきていた。住所は以前に教えてもらっていたが、実際に訪れるのは初めてだった。道路から彼女の部屋の窓を眺めたが、部屋の明かりは消えており、カーテンも閉め切られたままである。念のために部屋のドアをノックしたが、返事はなかった。
(どこへ行っちまったんだろう……)
それから隆太は毎晩彼女の部屋を眺めたが、愛は戻らない。一週間が過ぎ、半ば諦めの気持ちが混じり始めたある夜、愛の部屋に明かりが点いていた。
「愛ちゃん!」
気付けば矢のように飛び出して階段を駆け上がり、愛の部屋の扉を叩いていた。しばらく間を置いて、がちゃりと扉が開く。目の前には、よく似合うショートカットに赤い眼鏡を掛けた愛がいた。
「心配したんだぜ愛ちゃん! お、俺さあ――!」
言いたいことは山ほどあったが、なにひとつ言葉にならない。息を切らせている隆太を見つめる愛の瞳は、とても悲しげな色に満ちていた。
「隆太さん……」
「あ、いや、いいって。俺、怒ったりしてないし。えっと、なに言おうと――」
取り繕うように視線を泳がせた隆太は見てしまった。愛の後ろ――積み上げられた大小の段ボール箱と、家具が消えた殺風景な部屋を。
「え……え?」
「あの、立ち話もなんですから……中に入りませんか?」
隆太は誘われるまま、愛の部屋に上がり込んだ。部屋は寝床にするためだろうと思われるマットレスが一枚敷いてあるだけで、なにもかもが綺麗さっぱり片付けられていた。
「お茶飲みますか? ペットボトルのしかないですけど」
使い捨ての紙コップに注がれたお茶を飲み干すと、いくらか頭が落ち着きを取り戻す。愛は段ボールの前に座り込み、中身を整理している。
「な、なあ愛ちゃん。一体なにやってるんだよ。これじゃまるで引っ越しじゃないか」
食器の入った段ボールをガムテープで閉じてから、愛は立ち上がった。
「私、実家に戻ることになりました」
淡々と、愛は言った。感情の消えた、事務的な声だった。
「か、帰るって……」
「実家の父が病気で倒れたんです。元々具合が思わしくなかったし、両親には無理を言って上京させてもらっていたんです。けど、さすがにもう帰らないわけにはいかなくなって」
「地元に戻って……その後は?」
「父のコネで、大手アパレルの系列会社に就職が決まってます。それでこの一週間、手続きとかで向こうに戻ってたんですよ」
「ちょ、ちょっと待ってくれ。女優になる夢はどうするんだよ」
「仕方がないですよ。私には運がなかったんです。あーあ、ツイてなかったなあ、あははっ」
あっさりと言い切り笑う愛を見た途端、隆太の中でなにかが弾け飛ぶ。
「やめろよ、ダメなんだって! ここで演技なんかすんな!」
「……!」
「俺にだってそれくらい分かるよ。頼むから……今だけは自分に嘘つくなよ」
隆太は愛を抱きしめていた。痛くて苦しくて、気丈に振る舞う愛を見ていられなかった。
「ううっ……く、悔しいよ隆太さん……私、悔し……うわあああぁぁぁっ!」
愛は大きな声で泣きじゃくる。泣いて、泣いて、泣き続けた。信じれば夢が叶うと、隆太はこの時までは疑いもしなかった。この世にはどうにもならない事があって、誰もがいろんな事情や葛藤を抱えて生きていることを、骨身に染みて思い知らされた。そして今、彼の腕の中でひとつの夢が消えた。気が済むまで泣いた愛は落ち着きを取り戻し、隆太と並んで床に腰を下ろしたまま、ぽつりぽつりと語り始めた。
「ずっと黙っててごめんなさい。こんな事で心配かけちゃいけないと思って」
「俺、いつもバカみたいに自分のことだけ騒いでて……全然気付かなかった」
「ううん。隆太さんはなにも悪くないですから」
「俺さ、なんか力になれないかって考えてみたけどダメだった。金もないし学もないし……ごめん。本当に……ごめん」
うなだれたまま、隆太は唇をきつく噛む。今の自分があまりにもちっぽけで情けなくて、それ以上に悔しくてたまらなかった。
「泣かないで。私が東京で不安に押し潰されずにいられたのは、隆太さんのおかげです。あなたが真っ直ぐに夢を見て、いつも元気をくれたから……私は立っていられたんです」
愛は隆太の胸に顔をうずめ、安心しきった表情で彼をじっと見つめた。隆太はふと、いつか台本をもらって舞台の練習をしたあの時を思い出していた。
「私、隆太さんが好き。デートに誘ってもらったとき、本当に嬉しかったんです」
嘘も飾りもない本心から出た愛の言葉に、隆太は一筋の光明を見た気がした。これこそが、演技の辿り着く場所、目指す場所ではないだろうかと。隆太はあの時と同じに愛の頭を撫でてやり、彼女を抱き寄せた。
「お、俺も……初めて養成所の前で会ったあの時から、ずっと愛ちゃんが好きだった」
見つめ合う瞳は、少し悲しい熱を帯びて。ゆっくりと瞼を閉じる。そっと触れて交わしたキスは、涙の味が溶けていた。
「最後にひとつお願いがあるんです。聞いてもらえますか?」
「どんな?」
「私が東京を振り返らずにいられるように、大好きな人の思い出を……」
痛くてたまらない心をいたわるように、もう一度キスをして。触れあう互いの体温が、傷ついた心を熱く焦がしていた。
「ん……ちゅっ……んむっ」
長い長いキスだった。舌を吸い、唇をついばみ、離れても目が合えば再び唇を重ねて。飽きることなく続けるうちに、隆太も愛も熱で浮かされたように身体が火照ってきて服を脱ぐ。下着から解放された愛の胸を、隆太は優しく手で触れた。ちょうど手のひらに収まるほどの、柔らかで形の良いふくらみを弄っていると、愛は切ない吐息を漏らしながら、身体を隆太に預けてきた。
「はあ、はあ……隆太さん……」
「愛ちゃん、感じてるんだ」
「すごく恥ずかしいけど……気持ちいいです」
「今の愛ちゃん、すごく可愛くて色っぽいよ」
「ほ、ほんとですか? 嬉しいな」
はにかんだ笑顔を見せながら、愛は手を伸ばして隆太の頬に触れる。
「私……小さい頃からいつも、両親にいい子でいなさいって言われてました。だからいつもいい子のふりしてて、演技が当たり前になって。でも東京に来て、隆太さんと一緒にいる間はありのままの自分でいられて、とっても楽しかった」
「愛ちゃん……」
「だから、あの。今からちょっぴり悪い子になっても許してくださいね」
「へっ……おわっ!?」
そう言って、反対の手で愛は隆太のものをそっと握る。気分が高まってドキドキしているのと、自分以外の指が触れる感覚に、隆太は思わず変な声が出てしまった。
「熱い……それに固くて脈打ってる」
「うあ、ヤバイよ愛ちゃん。すげえ気持ちいいよ」
「もっともっと気持ちよくしてあげますから……んっ」
愛は隆太のペニスに顔を近づけ、ちろちろと舌を出して舐め始めた。普段の控えめで大人しい彼女からは想像出来ない大胆さに面食らいながらも、隆太は這い回る舌が与える快感に痺れていた。
「ちゅっ、ちゅっ……んむ……はぁーっ」
より熱く、硬くそびえ立つペニスを舐め上げた後、愛はそれを喉の奥まで呑み込むようにして、顔を動かし始めた。唾液と粘膜、そして絡みつく舌が絶え間なく快感を与え、絶頂へと誘う。我慢しきれなくなった隆太は、呻くような声で愛に言った。
「ダメだ、これ以上されたら出ちまうよ」
「はぁっ、はぁっ……いいですよ、このまま出して……あむ……んんっ」
口を離すどころか、愛は舌を亀頭に絡めてさらに刺激する。やがてペニスの先端から、堰を切ってあふれ出た精液が大量に放たれ、愛の口いっぱいに溢れていく。
「んっ、んぐっ……! けほっ、けほっ……!」
喉の奥で射精を受け止めた愛は、むせかえってようやく顔を離した。
「大丈夫なのか?」
「はぁ、はぁ……んくっ、はぁ……だ、大丈夫です。ちょっと驚いただけで」
「そんな無理しなくたって」
「今夜のこと忘れたくないから、どんなことだってしてあげたいから……だから」
「あ、愛ちゃん、そんな事言われたら俺、抑えが効かなくなっちまうよ」
「私も……来て、隆太さん」
すっかり濡れてぐちゃぐちゃになっている愛の秘裂を、隆太はいきり立ったペニスで貫く。狭く抵抗のある膣内を掻き分けるようにして、隆太はペニスを根本まで沈ませた。
「うぁ……痛……ぁ……!」
ふと我に返り、隆太は愛を見る。愛は目に涙を浮かべ、唇を硬く結んで痛みに耐えていた。ふたりが繋がっている部分からは、一筋の鮮血が滴り落ちていた。
「初めてだったのか? なんで……!」
「き、気にしないで。私は平気ですから」
「そんな辛そうにしてて平気なわけあるかっ」
「このまま中途半端に終わったら、ずっと後悔します。だから遠慮なんてしないで」
「……わかったよ。じゃあ動かすから」
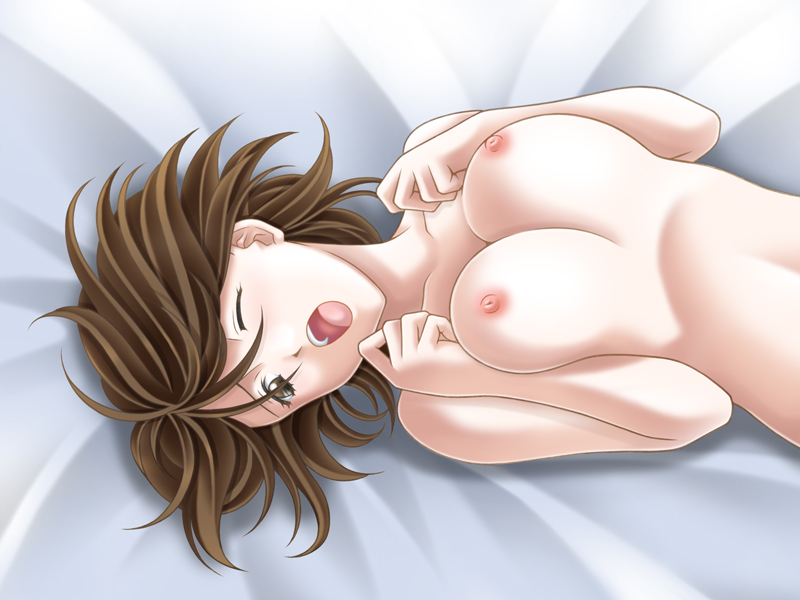
Copyright(c) 2009 netarou all rights reserved.