担任が言う。お前はどんな道を選ぶのかと。遠くへ続く道に目をやると、幾重にも分かれた道があり、その先は全てもやがかかっていて見通すことは出来ない。どれを選べばいいのか、俺はいつも悩んでそこから動けない。俺は同じ夢を、何度も何度も見続けていた。
(どうすりゃいいのか……全っ然、わかんねぇ)
代わり映えしない天井を眺めながら、一人呟いて俺は目を覚ます。布団の温もりが二度寝の誘惑を仕掛けてくるが、ここで負けてはいけない。
春休みも終わり、俺はめでたく高校三年生に進級した。学年末試験を、いつものごとく幼馴染のはるかの協力を仰ぎ、三日漬けで乗り切ったのも、今となっては良い思い出だ。喉元過ぎれば何とやら、である。とはいえ目に見えて日々が変わるわけもなく、いつもと同じように怠惰な朝を迎える。午前七時二十分。まだ半分寝惚けた目をこすりつつ、欠伸をしながらリビングへ向かうと、誰もいないテーブルに一人分だけ用意された朝食。トーストと、スクランブルエッグにベーコン。それにポテトサラダ。共働きの両親は朝早くから仕事に出て行く。温かい朝食を用意してくれるだけでありがたいってものである。朝食を手早くを平らげると、洗面所に向かう。歯を磨いて顔も洗い、髪にブラシを軽く通す。よし、完璧だ。
部屋に戻って制服に袖を通した頃、毎朝恒例のチャイムが鳴る。
(お、来たな)
玄関を開けると、見慣れた顔の少女が門の前に立ってこっちを見ている。和泉(いずみ)はるか。向かいの家に住む同じ年の幼馴染。くりっとした瞳の愛らしい顔立ちで、明るい笑顔をいつも絶やさない快活な少女だ。加えて保育園から高校まで、ずっと一緒の腐れ縁でもある。
「おはよう光太郎。新学年初日から寝坊はしなかったみたいだね」
「うむ、今日もお出迎えご苦労」
小さい頃はずっとボーイッシュなショートヘアだったが、今は僅かに亜麻色がかったちょっと癖のある髪を、肩に届くくらいまで伸ばし、美少女になったとご近所の評判も上々である。こうしてはるかと一緒に学校に向かうのが、俺のいつもの習慣だった。

「うーむ、しかし」
「どうしたの、人の顔じろじろ見たりして」
「毎度の事ながら、よく飽きないなー、と」
「なによー、はるかさんのお迎えに不満でもあるの?」
「や、逆の立場だったら、めんどくさくて放っておくだろうなって」
「あのねえ……光太郎が遅刻すると、私が先生に言われるんだよ。なんで坂井を呼んでこないんだー、って」
似てない口まねをして、はるかは口を尖らせた。
「学校の始まる時間が早すぎるんだよ。どうせなら昼過ぎからにすりゃいいのに」
「うわ、ダメ人間のセリフが出ましたよ」
「ダメ人間いうなっつーの」
「あっ、おはようございまーす。今日もいいお天気ですね」
登校中、いつもの通学路の家の前で、花壇に水をあげているお婆さんに、はるかは手を振って挨拶する。誰が相手でも明るく人当たりのいいはるかは、老若男女問わず他人を笑顔にできる魅力がある。学校でもファンが多く、並んで一緒に歩いていると、通りすがりの男達の視線を感じる事も多い。
「ん、なーに? また人の顔じっと見てさ」
「なんでもねえよ。自意識過剰っていうんだぞ、そういうの」
「失礼ねー。光太郎が見るから聞いたんでしょ。ていっ」
「ぐほっ、み、みぞおち……!」
鳩尾に、絶妙な角度で肘をもらってしまった。もちろんはるかも本気で力は入れてないし、所詮女の力なのだが、妙に狙いが正確なので結構侮れない威力である。
(でも、確かに最近――)
可愛くなってきたなと思う。雑談しながら目に入るはるかの横顔や、時々見せる何気ない仕草、そして風に乗って鼻腔をくすぐるシャンプーの香りに、不覚にもドキッとしてしまう瞬間があるのも事実だ。しかしずっと一緒に育ってきた身としては、はるかを特別な女性として意識はしていない。もちろん、単なる友達と言うほど遠くもないのだが。
お互いのことはよく知っているし、滅多にケンカもしない。だけど、べったりくっついているのとも違う、一歩だけ、間に挟んだ距離。それが暗黙のルール。俺たちには、これくらいの関係が丁度いいのだ。
「――でね、昨日のドラマに出てた俳優がさぁ」
他愛もない話をしながら歩いていると、後ろから俺たちを呼ぶ声がする。はるかは振り返って声の主に手を振っているが、俺は構わず歩を進める。すると背後から荒い息遣いがぐんぐん近づき、俺の肩を力一杯掴んで怒鳴った。
「シカトすんなっつーの!」
「よう、朝早くからダッシュとは精が出るな。体力作りか?」
「寝坊したんだよ、ったく」
息を切らせてぜーはー言っているこの男は、望月純(もちづきじゅん)。こいつもご近所さんで、はるか同様の幼馴染みだが、俺たちとは家が少し離れている。やっぱり小さい頃からの腐れ縁で、こいつと一緒にやらかしたいたずらやケンカなど、もはや回数を数える事さえ出来ない悪友だ。
「いいから呼吸整えろよ。ハァハァ言ってると変質者に思われるぞ」
「アホー、こんなナイスガイ捕まえてなにを言うかっ」
「新入生の女子生徒をチェックするためだけに、バイトして小型のデジカメ用意してたの誰だっけ? しかも高枝切りのハサミを改造して、高い所も容赦なしだぜイヤッハーとか騒いでたろ」
「ははは、いやだなあ光太郎くん。僕がそんなコトするはずがナイジャナイデスカ。ワタシ英国紳士デスヨー?」
「なぜ最後がカタコトだ。あと目を逸らすな」
「おいおい厳しいねー光太郎。宵ヶ浜(よいがはま)の黄金コンビとして培った絆はどこへ消えちまったんだあ」
「あのな、俺たち三年生でもうじき夏だぞ。いつまでもガキみたいな遊びしてられっか」
「俺だってもう卒業したっつーの。やっぱ遊ぶなら女の子だよな、ひっひっひ」
黙っていれば見れない顔でもないが、こいつは中身が問題なのだ。元野球少年だった反動か、伸ばした髪を茶色く染めて、いつもへらへらと笑っているから、同級生や一部の女子からは「顔も頭もフェザー級」だの「超うす」だのと、ありがたくない呼び名を頂戴している。基本的に根はいい奴なのだが。
「おはよう純くん。相変わらず俊足ねえ」
「はっはっは、少年野球の盗塁王は伊達じゃねぇぜ。これからは『ハヤテのもつ』と呼んでくれ」
「うーん、二十五点。響きに美しさがたりなーい」
「採点厳しッ!?」
「寝坊したぶんも差し引いてるからね」
「つーか俺も起こしに来てくれよ、はるかぁ」
「えー、だって純くんの家行くと、学校から遠ざかるし」
さらりと言ってのけるはるかと、しょんぼり肩を落とす純。そんな二人を見て、俺も笑う。他愛もない時間だけど、これが楽しくて心地良い。こんな関係がずっと続くのだろうと、この時の俺は疑いもしなかった。
上倉市宵ヶ浜は、太平洋に面して緩やかな弧を描く砂浜と、どこまでも広がる青い海を見下ろす高台にある。水平線の向こうで生まれた風が、潮の香りを乗せて吹き抜けていく。眼下に広がる海岸沿いの道を十五分も歩けば、俺たちの通う上倉学園が見えてくる。設備は整っているし、学業のレベルもそこそこ高い進学校だが、何よりも教室からの眺めが抜群というおまけ付きで、地元の生徒たちには結構人気がある。あまりののどかな環境に競争心が削がれ、大学進学希望者はうっかり一浪してしまう者も結構いる。学校のすぐ前にはローカル鉄道「江ヶ電」の駅があり、そのまま『上倉学園前駅』という。朝の通学時間になると、生徒をたくさん乗せたこの緑色の電車は、多くの生徒を吐き出しては、走り去っていく。駅から出て来た連中と踏み切りの前で合流すれば、学校の入り口は目と鼻の先だ。
「ん?」
ふと、駅の方から流れてくる生徒の一人に目が止まる。ふたつのおさげ髪を胸元に垂らした、見慣れない女子生徒だ。小柄で大人しい、たれ耳のウサギを思わせる可愛らしさがあるが、まぶたは寝起きみたいに重そうで顔色もよくない。同学年なら知らないはずはないし、下級生に違いない。女の子はあっちに行っては押し出され、こっちに寄っては弾かれて、見てるだけで不安になる弱々しい足取りだった。
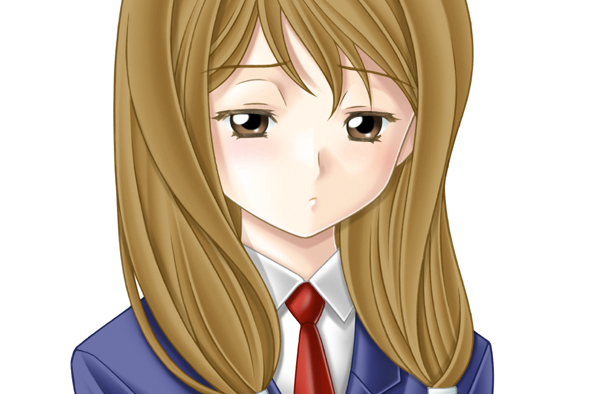
(うーん、大丈夫……なのか?)
「ねえ光太郎、ボーッとなに見てんの?」
「……ん、なんでもない」
「早く行こうよ」
「あ、ああ」
意識の片隅にその事を押しのけて、俺は学校へと急いだ。教室に辿り着けば、いつもと変わらぬ退屈な時間の繰り返しが始まる。教師の声を右から左に聞き流し、指先でペンを回したり海を眺めているうちに、チャイムが下校時間を告げるのだった。放課後は退屈から開放される嬉しい時間だが、はるかは水泳部の練習が、純は新学年になってから、よく分からない理由を述べてどこかへ消えてしまうため、最近は一人で帰宅することが多かった。
家に帰って一時間ほど経った頃、純が遊びに来た。いいものを見せてやると言うので部屋に入れてやると、デジカメとパソコンをケーブルで繋ぎ、大量の写真や動画のデータを展開していく。そこに収められていたのは、初々しさが眩しい新入生の女の子達の姿だった。
「――つまりお前は、このために姿を消していたってか」
「きしし、まぁな。情報収集は俺のライフワークってもんよ。見ろ、今年も豊作だぜー。お、この子可愛いなー。うわ、あの子胸でけぇなー、うひひ」
「もうちょっとマシなことに情熱注いだらどうなんだ」
「はぁ? 青春ど真ん中の男子にとって、これ以上に重要なことが他にあるかって」
「お前な、去年の今日も同じ事言ってなかったか? で、結局彼女できなかったろ」
「ぐっ……痛い所突いてくるねー光太郎さん。しかしですよ? 彼女がいないのはお互い様じゃね? じゃね?」
「その喋り方やめい。なんかムカつく」
「でもよー、新しい出会いを想像したらわくわくするだろ? それがきっかけで、退屈な毎日がパーッと変わるかも知れねーじゃん。光太郎はそう思わねえか?」
俺も健全な男子だから、女に興味はあるし恋人も欲しい。ただ、こんな風に相手を選ぶというのは品が良くない気がする。
(純はカッコ付け過ぎだとか言うだろうなあ)
「その通り、カッコ付け過ぎだぞお前は」
「心を読むなッ!」
「ふっ、光太郎の思考はまるっとぺろっとお見通しよ。この名探偵もっちーが、サクッと事件を解決してやるぜ」
「事件じゃないから。お前みたいな探偵いないから」
「まーまー。どんな子がいるかだけでも、知っておいて損はねぇって。な、黙って見とけ」
投げ渡されたジュースに口を付けながらビデオを見ていると、一年生たちに混じって見覚えのある後ろ姿があった。朝に見かけた、ふたつのおさげ髪の女の子だ。映像は下校時間だが、やはり人の流れに揉まれて息苦しそうである。
(どーも気になるなあ)
カメラが追っている一年生には目もくれず、俺は画面にチラチラと映る彼女だけを追っていた。弱々しい足取りで歩く姿を見ていると、手に汗が滲む。やがて女の子の姿は見えなくなり、ビデオもそこで終わった。密かに無事を願いつつジュースを飲み干すと、後は純と話したり、買ってきたばかりの雑誌を読んだりしてダラダラしていたが、何気なく窓の外に目をやると、西の海に沈む太陽が茜色に燃えていた。それを見た途端、俺はこんな事をしている自分が無性にたまらなくなって立ち上がり、純に言った。
「あー、部屋の中にこもってたらカビが生えそうだ。どっかに出かけようぜ」
「いいねえ〜。行きますか、青春の無駄遣いに」
「嫌な言い方やめろっての」
染みついた習慣に忠実に、俺たちは家を出て繁華街行きの切符を二枚買った。
「ふわぁ〜〜」
「ふわぁ〜〜あ〜〜っと」
俺の大あくびに釣られながら、純も眠たそうに目をこする。学校に向かって歩いちゃいるが、意識は半分寝ている。
「もー、大きなあくびしちゃってさ。ゆうべも遅くまで遊んでたんでしょ」
冴えない俺たちを見て、はるかはあきれた目線を向けてくる。
「いやー、つい盛り上がっちまって……ふわぁ」
「純がジュース変わりにあんなモン買ってくるから悪いんだぞ」
「えー、ジュースだろー。大人用ってだけで」
俺たちの後頭部を平手で叩いて、はるかは口を膨らませた。
「もう! 高校生がそんなの飲んだらダメでしょ!」
「ジュースだってば。ちょっとアダルトな味の」
「あーあ、最近は大人しくなったと思ってたらこれだもん。はあ……」
力一杯ため息をついて、はるかは肩を落とす。ほどなくして学園前駅の交差点に差し掛かると、ふたつのおさげ髪の女の子が駅から出てくるのが見えた。昨日よりさらに顔色が悪く、辛そうな表情をしているのが気になる。いつか倒れやしないかと心配していた矢先、本当に倒れてしまった。
「ちょっ……おい、しっかりしろ!」
驚いて固まってる奴らを押しのけて女の子に呼びかけてみたが、辛そうに呻くばかりで返事がない。俺はこの事を先生に伝えるよう純に頼み、彼女をそっと背負うと、できるだけ揺らさないように歩き出した。女の子は俺の背中に体を預けたまま、糸が切れた人形のようにぐったりとしていた。

「――で、どうですか響(ひびき)先生」
保健室のベッドに寝かせた女の子を見ながら、俺は校医の響さくらに訊ねる。白衣を着てなければ校医とは思えない美貌とスタイルの持ち主だが、倒れた女の子への処置は的確で、脈や熱を測る動きは素早く無駄がない。響先生の邪魔にならないよう、ベッドから少し離れた場所で俺達は見守っていた。
「心配ね……この子、急に倒れるんだもん」
「悪い病気とかじゃねーッスよね? ね?」
「大丈夫、ちょっと休んでればじきに回復するわ」
響先生はそう言い、優しく微笑みながら俺たちの行動は立派だったと褒めてくれた。
それからはいつもどおりの日常で、退屈な授業も滞りなく進んで昼休み。購買で買ったイチゴ牛乳とサンドイッチの詰め合わせを食べていると、クラスメイトが俺に会いに来ている奴がいると言うので、かじりかけのハムサンドをくわえたまま廊下に顔を出した。そこには、背が低くてふたつのおさげを胸元に垂らした、あの女の子がちょこんと立っていた。
「え、えっと、は、はじめまして。あのう、坂井光太郎先輩……ですよね?」
「ああ。そうだけど」
「あ、あのっ、倒れた所を助けてくれたそうで、ありがとうございました。私、二年B組の白川雛子(しらかわひなこ)といいます」
女の子――雛子は緊張した様子ながらも、両手を前に合わせ、丁寧な動作でお辞儀をした。
「で、なんの用で来たんだい?」
「え? だから、朝のお礼をと……」
「あーあー、そのためにわざわざ」
「う……もしかして、お邪魔だったでしょうか」
「ちょっと待ってな」
「はい?」
「礼を言われる奴は他にもいるから」
俺ははるかと純を呼び、今朝の女の子が来た事を告げた。二人のことを紹介すると、俺のときと同じように、女の子は丁寧な動作で深々と頭を下げた。もう大丈夫なのかとはるかが聞くと、雛子はうつむいて「ご迷惑をおかけしました」と謝った。
「気にしなくていいよ。困ったときはお互い様だもんね」
「あ、ありがとうございます」
はるかの笑顔に幾分救われたようで、雛子の表情も少し明るくなる。俺の隣で純も笑っているが、いつもへらへらしてるこいつは、あまり変わり映えしない。
「望月先輩も、ありがとうございました」
「いやいや、どーって事ないさ。『義理人情のもつ』と呼ばれたこの俺が、困ってる子を放っておけるはずがないぜ。わっははは」
初めて聞く呼び名だが、いつもの事なのでツッコミは心の中でしておいた。雛子はもう一度丁寧にお辞儀をして、自分の教室へと戻っていった。三人で彼女の背中を見送っていると、純が滅多に見られない真顔で口を開く。
「なあ光太郎……新鮮だな」
「ああ、新鮮だな」
同じタイミングで頷く俺と純を見て、はるかはキョトンとしている。
「新鮮って、なにが?」
「白川雛子か……おしとやかで儚げで、はるかとは正反対の――」
言い終わる前に、思いきり足を踏まれた。
「おっおおお……!」
「ふーんだ、どーせ私はおしとやかじゃありませんよーだ」
はるかはそっぽを向いて拗ねてしまい、結局その日は口を聞いてもらえなかった。
(ちくしょう、なんで俺だけ。純も踏まなきゃ不公平だろーが)
「ひっひっひ、日頃の行いが悪いんだよ光太郎は」
「だから心を読むなっっつーの!」
「でもよ、なんだかワクワクしねーか?」
「なにが」
「俺たちは今、新しい出会いをゲットしたんだぜ。この先……そう、夏になればもっともっと大きな変化が待っていると俺の第六感、名付けてもっちーセンスが告げているッ」
「あー、イチゴ牛乳が美味い。この香りと甘ったるさが、いかにも青春って味だな」
「シカトすんなっつーの! ていうか前も同じ事言った気がするぞコレっ」
この時は気にも留めなかったが、純の言葉が間違っていなかった事を知るのは、もっとずっと後になってからのことだった。
「はうっ」
寝心地の固いベッドから飛び起きた俺を、仕切りのカーテンを開けて響先生が覗き込んでいた。
「騒がしい目覚めねえ、坂井くん」
響先生は少し屈み込んでいるから、服の胸元が開いて豊かな膨らみがチラチラと見え隠れしている。思春期の男子なら、どうしても目が釘付けになってしまう見事さだ。
(おお、ラッキー)
目覚めて早々に鼻の下を伸ばしてるのはマヌケだと、理性という名の俺が言う。名残惜しさを感じながら、咳払いをして誤魔化しておいた。
「……すんません」
「ふふ、女の子に逃げられる夢でも見てた?」
ズバリ言い当てられて、俺は驚いた。女の勘というものだろうか。見ていた夢は枝分かれした道の前で悩む、いつもの奴だったが、今日は少しだけ違った。俺の前に女の子が現れ、分かれた道のひとつを選んで歩いて行くのだ。誰なのかは分からないが、彼女が進む方向に自分も行かなければならないと強く感じ、俺は後を追いかける。だが足がふわふわと浮いて前に進まず、大声で女の子を呼んだところで目が覚めた。夢の意味が分からず首を傾げる俺に、響先生はコーヒーを淹れてくれた。いつも棚の奥に隠してある、専用のカップに注がれた黒い液体はインスタントではないいい香りを漂わせる。
「こうやって坂井くんとコーヒー飲むのも、何度目かしらね」
「三年になってからは初めて……のはず」
「そうね、前に比べたらずいぶん顔出さなくなったわねえ。えらいえらい」
俺の頭を軽く撫でて、響先生は自分の椅子に腰掛ける。昔を思い出しながら飲むコーヒーの味は、俺の笑いも苦くさせた。ここへ来る理由など単純で、時々ベッドでくつろぎたくなるという、ただそれだけだ。
「なんつーか、あんまりサボってると、いい加減ヤバいかなーと」
「へえ、少しは危機感が出て来たのね」
「あの、響先生。ひとつ聞きたい事があるんですけど」
「エッチな質問なら断るわよ」
「そりゃ残念――って、そうじゃなくて。響先生って、悩みとかあるんすか?」
「もちろんあるわ」
「どんな?」
「ヒミツ」
「……ですよね」
切り返しの巧さは、さすが大人と言うべきか。響先生とはそこそこの付き合いになるが、個人的な事はほとんど分からない。端整な顔立ちの美人なだけに、余計ミステリアスで底の見えない人だ。
「もしかして坂井くん、悩み事でもあるの?」
「いや、なんでもねっす」
「話したい事があれば、遠慮せずに言うのよ。いつでも相談に乗るから」
相談しようにも、あまりに漠然としすぎていてどうにもならない。相談する内容をまず相談しなければ、といった感じだ。
(……もうちょっと真面目に考えてみるかな)
ぼんやりと窓の外を眺めれば、高く昇った太陽が宵ヶ浜の海を照り付けている。
夏はもう、そこまで近づいていた。